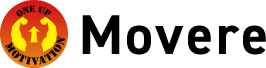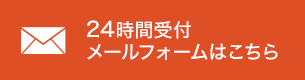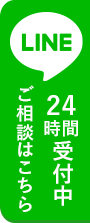さいたま市浦和区のパーソナルトレーニングジム
Movere(ムーバー)代表パーソナルトレーナーの佐藤択磨です。
4月になったら毎朝かならず走ろう!とか、
筋トレは毎日やろう!みたいに決めたけど、
やる気が出ずに、いとも簡単に続かなかったことってないですか?
運動習慣を付けようと意識したことは
色々あると思いますが、
やる気なんていりません。
やる気の継続性が出せない人は、
環境はもちろん自身に対する
セルフマネジメントの仕方を知らないのです。
ということで、
- そもそもやる気ってなに?
- どうやったらやる気は出るの?
- 頭よりも身体が先。
- たったの3ステップと目標設定の超常識!!
そんな話をさせて頂きますね。
やる気の正体
意外と当たり前に使われているので
知らないかもですが、実は
やる気という言葉は脳科学的には存在しない概念なのです
どういうことかというと
×『やる気が出ない』のではなく、
○『やる気を出さない』という選択をしただけ。
これらが脳科学の研究で明らかになっている解釈です。
人間がやる気に満ち溢れているときは
脳内に分泌されるホルモンでもある
ドーパミンの働きが大きく影響します。

このドーパミンとは興奮作用のものなので、
実際になにかしらの行動をしないと分泌されません。
つまり脳科学的な説明をすると
「やる気を出してから運動をする」のではなく、
「運動を始めてからやる気が出てくる」
というのが正しい方法だということです。
意図的かつ効果的に『やる気』を出すには?
もともと運動へのハードルが高い人は、
自分がほぼ確実におこなえる目標設定に
しないとそもそも行動を起こせません。
例えば毎朝10kg走る、、、そう決めた時に、
・キロ何分で走りますか?
・そもそも成人男性の平均タイムは?
・どんなウェアで走りますか?
・シューズは硬め?柔らかめ?
・雨が降ったらどうしますか?
こういった質問に対して、
イメージができていない人は
走るまでに至りません。
また走ったとしても続かないのです。

続かないことg¥が積み重なると、
「あぁ、けっきょく続かなかったな」
という自己肯定が下がる方に働きます。
つまり、、、
『出来るじゃん自分!!』
こういった小さな成功体験を積み
重ねることでやる気も継続されるし、
自己肯定感も上がりセルフイメージを
高く持ち続けることが出来るのです。
ちなみに余談ですが、
人は怒りや悔しさ、また幸せな
ことでもやる気は起こせます。
ドーパミン効果は4ヶ月
やる気の持続性は怒りのもとである
ドーパミンで効果は4ヶ月。
セロトニン効果は4年間
幸せホルモンのセロトニンであれば
平均4年間もやる気が継続される
なども近代ではわかってきました。
やる気の具体的な起こし方
ここまで聞いて脳科学的観点での
やる気の概念や起こし方は理解できましたか?
習慣を継続する難しさはダイエットでも
勉強でも体感していくなかで磨かれていきます。
あれこれ考えずにとりあえず本を読んだり、
家で何気なしに片付けをして気分が乗ってきて、
ついでにストレッチとかやることってありますよね?
脳科学では身体を動かすのが先で、
頭で考えるのはずっとあとなんです。
ここが今回の記事のメインメッセージです!
それでもやる気を起こす際にどうしても
自分の課題や目標を大きく設定しがちになります。
またこれは厄介なことに真面目な人ほど
この負のループに陥りやすいのです。
そんな方々のために、脳科学的に
正しい目標設定の方法もお話します。
目標設定は続けること
ちょうど3年前の投稿が出てきましたが、
これもぼくなりに行えていた良い習慣だったんですよね。
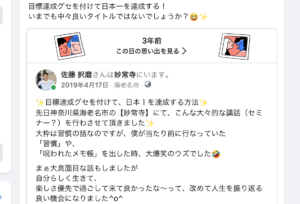
そしてその目標を超えていくため、
ステップアップの仕方を次の文章でまとめますね。
目標設定で重要な”3つの超常識”
運動習慣を形成するのにいちばん
難しいことはやる気を起こすのではなく
最終的に継続させることです。
一過性のやる気は何らかの形で出して
運動なり部屋の片付けなりはしたことはありますよね?

でも続かなかった結果がいまこの記事を
読んで痛いほど身に染みているはずです。
ということで最後に意図的に
やる気を起こさせる具体的な
方法をお伝えしていきます。
①ベイビーステップ
ベイビーステップとは、
「赤ちゃんでも超えられる、
または渡れるほどの高さ」のこと。
つまり目先の目標でも良いので
一歩でもその夢や目標に近づく
小さな目標(行動)を設定します。
例えばランニングであれば、
・Tシャツに着替えるとか、
・靴を履くとかでも良いです。
間違っても
・毎日10分ランニングとか、
・ジムに週/3回は行くとかではないですからね。
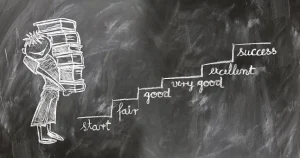
文頭に上げましたが、
雨が降ったりの外的な要因も含まれると、
10分のランニングは外に出ることだけでも
いきなり反り立つ壁となり得ます。
そのもっともっと前段階で良いですから、
必ず行えそうな目標設定をすることが
やる気を引き出すコツとなります。
②セルフ・エフィカシーコントロール
セルフ・エフィカシーとは
『ある行動をうまく行うことが
できるという自信のこと。』
人がその行動へのやり甲斐や生き甲斐を
強く感じるとその行動を行う可能性が
高まったり強まったりするのです。

またエフィカシーとは感情的な説明で、
自分が適切な行動を遂行できるかどうかの
認知や遂行能力にも影響を与えることが分かっています。
どういうことかというと、
その行動に取り掛かる前や最中で、
『出来るかな〜?どうかな〜?』と
期待感のある状態を指します。
50:50(フィフティーフィフティー)の
法則とも言うのですが、
例えばランニングで目の前の4〜5m先を
走っている相手を見たら追い抜けそうな気がしませんか?

またこれがゴール間近であれば、
身体はとうに限界をきていても
火事場の馬鹿力を発揮したりします。
人間はありとあらゆる場で
感情によって左右されますが、
それを意図的に作れるのが
セルフ・エフィカシーです。
心理学者のアルバート・バンデューラが
「社会学的学習理論」で提唱しましたが、
『人間の成長には優れた他者を
模倣することが重要だ。』
という理論を打ち立てたものです。

つまり、目の前の恐怖の克服をすることで
大いなる自信や優越感を得られるのがこの
セルフ・エフィカシーの重要なところです。
③自分にはできるという自己効力感を鍛える
自己効力感を簡単に言い換えると
『自分はできる』と信じる気持ちのことです。

できると信じられるからこそ、
チャレンジ精神が高まったり、
セロトニンが大量に放出されてやる気が継続されます。
自分にはできるはずという達成経験の積み重ねが
自己効力感を確固たるものにしていきます。
困難な目標であればあるほど
この上積みは期待できますが、
最初から無理な設定をすると
効果は逆に働きます。
謙遜が美徳と勘違いをして
「自分は能力が低い」と思い込んいたり、
自分の能力を見誤っているのが
日本人の特徴でもあります。
自分の殻を破るにはいつだってこうした
認知の積み重ねが達成経験に変化していきます。
「これぐらいなら出来るかも」っと、
ぜひ気軽に設定して行っていってくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
3ステップにまとめると少し最後の説明を
もう少し理解をしていく必要があるかもです。
ようはちょっと頑張ればできそうな
目標設定を毎回たてて下さい。
最初の一歩目はとにかく小さく、赤ちゃんでも
乗り越えられるベイビーステップを意識。
そうすることで自己効力感は上がり続けます。
ぜひ自分にとっての達成感や
成功体験を積み重ねていってくださいね。

それでは皆さま、今後とも
Movere(ムーバー)パーソナルトレーニングジム
@浦和を、どうぞよろしくお願い致します。
![]()
株式会社ワンアップモチベーション
パーソナルトレーニングジムMovere
代表取締役 佐藤 択磨
個別の相談はこちらから
※ラインでのやり取りになりますが
気になる点がございましたらお気軽にご質問をお待ちしています。